テレビの想い出
これは過去に書いたエッセイです。(2020年3月31日)
これは、私のトラウマの話である。
子供のころ、テレビを見ない子供だったと書くと、「おそらく親が見せてくれなかったんだろう」と思う方も多いだろう。
しかし、私の場合はそうではなかった。私はテレビが怖かった。例えば高所恐怖症とか、閉所恐怖症とか、そういう特定の何かに対する恐怖症と同じように、テレビを恐怖し、その中で動く映像を見ることに強い苦痛を感じる子供だった。
はじまりのことをよく覚えている。おそらく自分が4歳か5歳のころだったと思う。
私が3歳の時に交通事故で父を失った我が家は、明るい雰囲気とは言えなかった。母はよく泣いていたし、私自身は父を失ったそのことよりも、母に泣かれたり、当たられたりすることに動揺していた。当時の私には死という概念はわからなかったが、事故当時の記憶も自分の中にうっすらと残っていた。
東京から田舎に引っ越し、保育園も転園した。通常ならそこで人間関係に支障をきたすところだが、ありがたいことに野生児の自分には田舎の空気の方があったらしい。東京にいた時に通った子供園はなんとなく居心地がわるく、「しゅんくん」という名の友達と砂の城ばかり作っていた記憶があるが、田舎の保育園にはすぐなじんで駆け回ったことをよく覚えている。
そんなある夜のことだった。私は家の中をうろうろ歩き回り、母がテレビを見ているうしろを通りかかった。ふとテレビの方を見ると、死体の山が積み重なったモノクロの映像が流れている。私は硬直した。見ていると今度は大量の眼鏡が積み重なったものに移り変わった。今考えればあれはアウシュビッツか何かのドキュメンタリー特集番組のようなものだったのだろう。しかし当時の私にはそんなことの意味は全く分からず、ただ恐怖のみが自分の中に満ちた。
おそらくだが、幼い私の中で事故の記憶や恐怖の映像がごっちゃになったのだと思う。その日から、私はテレビが見られなくなった。映像を見ると、次の瞬間に人が残酷な殺され方をするのではないだろうか、見るに堪えない映像が出てくるのではないだろうかと思ってしまうのである。
これに拍車をかける出来事が、オウム真理教事件だった。おそらく6歳とかだったと思う。ニュースのアナウンサーの切迫した声、流れる奇妙な映像の数々、これらは私の恐怖症を補強するのに十分だった。
さらに、保育園や小学校で見せられる交通安全ビデオの中で語られる交通事故、避難訓練のビデオで語られる災害が私の恐怖症を確実なものにした。映像は怖いものなんだ。見れば、その中では確実に誰かが死んだり、事故が起きたり、火事や地震が起こるんだ、と。
まわりの子供たちはテレビアニメがみな好きで、当時はやっていたセーラームーンごっこなどは保育園でも大人気だった。私もそこに参加しないわけにはいかなかったが、アニメを見ていない私にはセーラームーンのことなどさっぱりわからない。
母はおそらく初めは私がテレビを見ないことを喜んでいたと思うが、ある時点で私のテレビ嫌いがおかしいことに気づいたらしい。何しろ天気予報でさえ嫌がるのだ。ディズニーの映画を見せようとしても、私は『シンデレラ』以外は見られなかった。ちなみになぜシンデレラが見れたのかというと、恐怖症が始まる前に見た楽しい記憶があったのと、悪役があくまでも一般人で恐ろしい魔物に変身したりしないから、と当時の私は考えていた。(今考えると笑える)
セーラームーンのような戦闘シーンがある映像は論外である。今でも、セーラームーンのアニメを見るたびに逃げ出したのを覚えている。友達の家に遊びに行くのも、途中でビデオを見せられる時間があると思うと憂鬱だった。当たり前だが映画にも行けなかった。
しかし、奇妙なことに私は文章や漫画だと情報を手に入れるのが怖くないことに気づいた。ある日、おそらく心配した母がセーラームーンのテレビガイドブックを私に買ってくれたのだが、それを読むのは全く怖くなかったのである。むしろ、キャラクターたちをながめるのは楽しくてたまらなかった。それを読めばセーラームーンごっこにもついていけたし、アニメの話にも参加できた。
それに気づいた私は本が大好きになった。幸いにも家には本がたくさんあり、読むべきものには困らなかった。小学生になってからは拍車がかかった。テレビは一切見れないが、本の中では殺人事件がおころうがなんだろうが、別に気にならないのである。図書室にあるあらゆる本を読み漁った。ミステリーが気に入り、ホームズやアガサ・クリスティ、江戸川乱歩などをたくさん読んだ。
象徴的な出来事をよく覚えている。
小学校も中学年になると、戦争のことを取り扱う授業が出てくる。その一環で授業で『火垂るの墓』を見ることがあった。クラスメイトは映画を観られることを喜んだが、私は嫌で嫌で仕方なく、身を縮めて目をつぶり耳をふさいだ。火垂るの墓はまさにわたしの恐怖症をえぐってくる内容のもので、怖くて仕方なかったのである。先生はあまりにおびえる私をかわいそうに思ったのか、「図書室に行っていいよ」と言ってくれた。
私はほうほうの体で図書室に逃げ出し - そしてそこでシャーロックホームズが連続殺人事件を解決する話を読んでいたのである。今考えてみれば、『火垂るの墓』を視聴して戦争の残酷さを知り、このようなことを起こさない、と子供心に思えるようになることはシャーロックホームズより教育的に必要なことである。しかし私はそれが出来なかった。
というわけで私は一概に「子供にはテレビを見せずに本を読ませなくてはならない!」というのは間違っていると思う。大事なのはコンテンツなのだ。私のようにテレビを観なくても殺人事件の話ばかり読んでいれば、結局は同じなのである。
小学校4年生を過ぎると、私はお小遣いをもらうようになり、また、本が好きだということは親戚中に知れていたので、お土産というと図書券をもらうようになった。
うちは建前上の規則としては漫画ではなく小説を読もう、というものがあったにせよ、実際のところその規則は正常に機能していなかった。推奨して買ってくれることはないものの私が自分のお小遣いで漫画を買う分には文句は言わなかったのだ。
私は電車に乗って一人でピアノ教室に通うようになっていたので、一人の時間にある程度自分勝手に使えるお金、というのを持つようになっていた。それは貴重なお金だった。ナルト、ワンピース、フルーツバスケットから始まりたくさんの漫画を読んだ。図書券はすべて漫画になった。
小説は買ってもらえたので、青い鳥文庫や岩波児童文庫など、子供向けの文庫を読み漁った。「夢水清志郎」とか、「青い天使」とか「パスワード探偵団」とか、岩波文庫から出ていたメリー・ポピンズやプーさんなども原作で読んだ。(しかしメリー・ポピンズもプーさんも怖くて映像では見られなかった)福音館書店の子供向け文庫も読んだ。ジュール・ヴェルヌのSFにはまり、ロビンソン・クルーソーの冒険にもはまった。ピーター・パンも好きだった。
一方で、私の映像嫌いに革新的なことが起こった。私は映画を観れるようになったのである。
きっかけは、『102』という101匹わんちゃんの続編を、実写化したものだった。たくさんいるダルメシアンの中に、突然一匹黒ぶちがない、真っ白な子犬が生まれ、その犬が主人公(主犬公?)となってクルエラに立ち向かう、というごくかわいらしいストーリーである。私の興味を惹いたのは、その主人公の犬が「オッド」という名前だということだった。今考えてみれば odd という英単語を名前にしたのだとわかるが、当時の自分にとっては自分の苗字、おとます にどこか発音が近いものだという認識しかなかった。私はディズニーストアに行く時ですらも店内で流れる映像が嫌いだったのだが、『102』はちがった。走り回るたくさんの子犬たち、そしてその中にいる一匹のまっしろな子犬・・・。
私が母に『102』に興味を持っている旨を伝えると、おそらく母は私のことをずっと心配していたのだろう、私の友だちも一緒に車に乗せて『102』を見に行っても良いという魅力的なプランを提案してくれた。
私は『102』当日、死ぬほど緊張していたが、全くいつも通りどころか、映画を見に行くことになってテンションがあがっている友達にはそれをさとられたくなくて努めて平静にふるまった。初めての映画館は暗くてポップコーンの香りがして、まるで異世界のようだった。
覚悟を決めて、初めて見た『102』は私の恐怖症を完全にひっくり返した。こんなにかわいくて面白いものは見たことがなかったのである。グレン・クローズが演じるクルエラもおかしさと怖さを絶妙に兼ね備えていて、笑ってしまう。
観終わった後、わたしは「映画がこんなに面白いなら、そりゃみんな授業で喜ぶわけだ」と初めて納得した。どこか拍子抜けした気分ですらあった。
さらに、私の大好きな小説『ハリー・ポッターと賢者の石』が映画化したのも大きかった。本ばかり読んでいた私は学校ですでに「ハーマイオニー」と呼ばれていたので、こちらも身近に感じていたのである。
「ハリー・ポッター」の映画のおかげで私は完全に映像恐怖症を抜け出すことが出来た。時を同じくしてユニバーサルスタジオジャパンに行き、バック・トゥ・ザ・フューチャーやE.Tに興味をもったのも大きい。いきなりこんな名作たちが自分のまっしろな「映像」という分野に現れたのだから、私は映画に夢中になってしまった。
本が好きだった私は基本的に原作を読んでから映画化されたものをみることが多かったが、『ロード・オブ・ザ・リング』は映画から見た。私はこの作品が今でも大好きだが、これを見た時の感動はわすれられない。映画と本、どちらも素晴らしい作品が両立するのだと教えてくれた作品だった。
一方で、わたしはテレビを未だに見なかった。もう恐怖はなかったが、日本のバラエティー番組には独特の「語られないルール」のようなものがあり、それを知らないで見ても面白くないのである。今まで全くテレビを見ないで育ってきたわけだから、テレビの有名人を知らない。知らない人たちが知らないことをぎゃあぎゃあとしゃべっているようにしか見えない。お笑い芸人の「ネタ」も何が何だかわからない。友達が楽しそうにまねする一発ギャグも何が面白いのかわからない。なんだか暴力的に見えていた。
私がやっとバラエティー番組を「面白いな」と思えるようになったのは中学生も後半になってからだったと思う。当時、『トリビアの泉』や小島よしお、オードリーなどが出始めていて、わたしはやっと友達に合わせて笑うだけでなく、心から「面白い」と思えるようになってきていた。
高校に入ってからは『ガキの使いやあらへんで』のダウンタウンのトークを観てハマったりして、やっと普通の高校生になった。
現在、私はいまだにテレビ番組を見る習慣はあまりないが、ネットが発展した今では逆に時代が私に追いついてきている様相すらある。おかしなことだが私はYoutubeやNetflixは大好きである。一人暮らしを始めてからテレビを持って暮らしたことはほぼないが、もう時代がそれを要求してこない。
ただ、同年代の人と話しているときですらもジェネレーションギャップのような、ぽっかりと抜けた何かを思い知らされるときは今も多い。例えば、セーラームーンもポケモンもキッズウォーも私は観ないで育った。だから、そういう話になっても私には語るべき思い出が何一つないのだ。面倒くさい時は「おもしろかったよねえ」などと話を合わせるが、私の知識は高校生や大学生になってウィキペディアなどから得た後付けの知識なので、原体験のなつかしさ、美しさはどこにもない。
今日は2020年の3月31日である。なぜ私がこのエッセイを書いたかというと、それは前日に志村けんがCOVID19により併発した肺炎によってなくなったからである。
私にとって志村けんほどわけのわからない人はいなかった。ダウンタウンは高校になってからもずっと活躍していたから面白さをリアルタイムで味わえたが、志村けんの全盛期はおそらく私の映像恐怖症期と完全にかぶっていた。
みんなが爆笑しているバカ殿様も、バラエティー番組の前提条件を理解していない私には何も面白くなかったし、むしろ恐ろしさの方が勝っていた。高校生や大学生のころには志村けんの番組を見ることはなかった。
皆が志村けんをいたみ、どれほど偉大な人で尊敬していたか語る。しかし私には何もわからない。出ていた番組も、ほとんど知らない。
しかし、私の中でもひとつ何かが終わったことは感じた。私はもうあのわけのわからない番組を面白いと思っているふりをしなくてもよい。一つの時代の一人の巨星がおちたことによって、私の中にあった空洞はもう埋められる必要がなくなったのだ。それにわたしはホッとし、またそれが埋まらなかったことを残念に思う。テレビを全く見なかったわたしにすらそう思わせるという意味で、かの人は偉大なひとだったのだろうとなんとなく思う。
人をかたちづくるという意味で、映像や本、音楽もゲームもとても大事である。テレビを観ないで育った私には日本のバラエティーの共通言語がいまだによくわからないこともある。昔はそれをコンプレックスに感じていたが、今はもうそれもない。べつのもので満ちているからだ。それは時に教育に推奨されるもので、時には推奨されないもので満ちているが、今は自分の中ですべてが混ぜ合わさり、自分という何かを構成する一部分となっている。何を食べて生きてきたかで体ができあがるように、何にふれてきたかで人間の魂はできている。不思議である。
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。








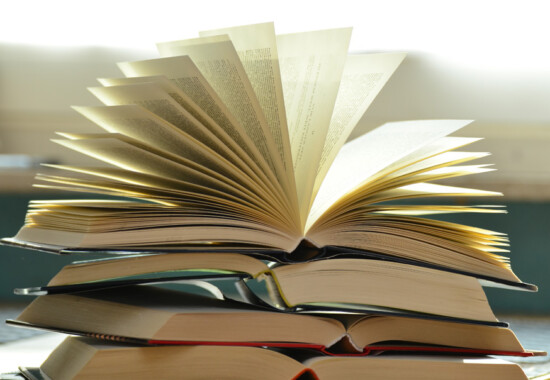
この記事へのコメントはありません。